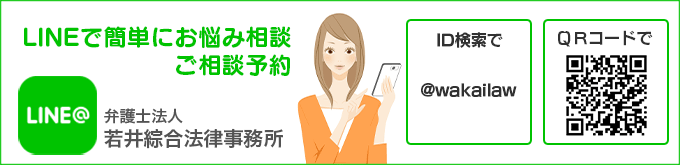- ネットで脅迫されても警察は動かないのではないだろうか…
- もし動いてくれなかったらどう対処すればいいのだろう…
こういった疑問を抱えていませんか?
そこでこの記事では、これらの疑問や悩みを解消すべく、恐喝・脅迫に強い弁護士が以下の点についてわかりやすく解説していきます。
- ①ネットのどんな書込みが脅迫罪になるのか
- ②ネットは匿名だが、脅迫した人が特定できるのか
- ③ネットの脅迫で警察は動かないのか
- ④警察に行く前の証拠の保全方法
- ⑤ネットの脅迫で警察が動かない場合の対処法
およそ4分ほどで簡単に読めますので、ネットで脅迫されてお困りの方は最後まで読んでみて下さい。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
ネットのどんな書込みが脅迫罪になる?

脅迫罪とは、本人や本人の親族の、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知(「害悪の告知」といいます)して人を脅迫することで成立する犯罪です。
そして、ネットに害悪の告知を書き込んだ場合も脅迫罪は成立します。
例えば、ネットの掲示板に「〇〇を殺す」と書き込めば生命に対する害悪の告知となり、「〇〇の裸の画像を拡散(流出)します」などと書き込めば名誉に対する害悪の告知となり脅迫罪に該当します。
ただし、脅迫罪の対象はあくまでも「本人や本人の親族」ですので、「お前の彼氏を殴る」「アナタの友達の家に火をつけてやる」といった書き込みは脅迫罪に当たりません。
また、ある書き込み内容が脅迫罪に当たるかどうかは、一般人が怖がるかどうかで判断されます。
例えば、twitterやFacebookなどのSNSで、「お前のIPアドレスを調べて住所特定して殺しに行ってやる」と書き込みされた場合でも、被害者がITに詳しい人であればそれが実現不可能であることがすぐにわかりますので、怖いと感じることはないでしょう。
しかしITにさほど詳しくない多くの一般人からすれば、本当にそういったことが出来てしまうのではないかと畏怖することが考えられますので、脅迫罪が成立します。
無差別の殺害予告や爆破予告の場合は?
例えば、「これから小学校に乱入して生徒を殺しまくる」「〇〇駅で爆弾を爆発させる」という無差別殺害・爆破予告をネットの掲示板に書き込んだとします。
一見、脅迫罪が成立するケースにも思えますが、このような犯行予告のケースでは加害の対象となる人が広範囲で明確ではありません。
そのため、脅迫罪ではなく、警備をすることとなった警察や対象とされた機関(今回の例でいえば小学校や駅)の正常な業務を妨害したとして、威力業務妨害罪が一般的には適用されます。
ネットは匿名だから脅迫した人が特定できない?
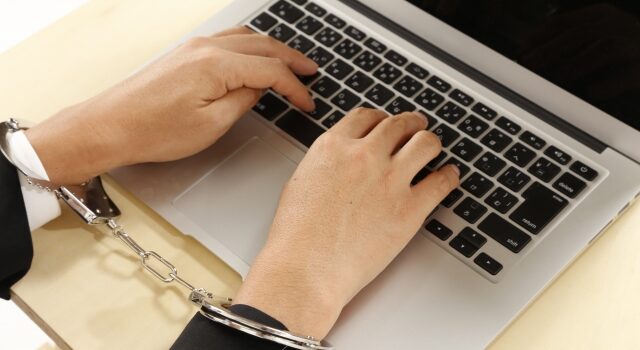
できます。
警察は捜査関係事項照会という制度を利用して、脅迫の書き込みがされたサイトの運営者に書き込みした者のIPアドレスの任意開示を求めることができます。令状捜査であれば強制的に開示させることも可能です。
IPアドレスが分かれば、上記と同じ手続きでプロバイダに書き込みした者の契約者情報を開示してもらい、書き込みした者の氏名や住所を特定することができます。
また、一般人であっても、プロバイダ責任制限法という法律に基づいて、発信者情報開示請求という手続きで脅迫の書き込みをした人の身元を調べることができます。
書き込み犯人の身元がわかれば、脅迫により被った精神的苦痛に対する慰謝料請求の民事訴訟を起こすことも可能となります。
ネットの脅迫で警察は動かない?

「ネットで脅迫されても警察は動かない」といった情報がそれこそネットで見受けられますが、これは間違いです。
例えば、令和2年にマスコミ報道されたネット脅迫の逮捕事例として、以下のようなものがあります。
- 掲示板「5チャンネル」に大阪府の吉村知事を「殺害します」と投稿した男を脅迫容疑で逮捕。
- アニメ「けものフレンズ」の監督を名指しして、掲示板「5ちゃんねる」に「ナイフでメッタ刺しにして殺す」などと書き込んだ男が脅迫と威力業務妨害で逮捕。
また、令和3年2月4日にも、お笑い芸人「おぎやはぎ」に対しネット掲示板で殺害予告をした男が脅迫容疑で逮捕されています。
これはあくまでも被害者が有名人であるから報道された一例であって、警察庁の広報資料によると、令和2年にはネット脅迫事案の検挙数は349件もあります。
被害者が通報しないと警察は動かない?
そんなことはありません。
脅迫罪は親告罪(被害者が刑事告訴しないと起訴できない犯罪)ではないため、脅迫的な書き込みを、被害者以外の第三者が警察に通報したり、警察のサイバーパトロールによって発覚したような場合でも、捜査が開始され逮捕に至ることもあります。
ただし実務上は、殺害予告等の重大事件を除き、書き込みされた被害者本人による被害届や告訴状の提出がなされないと警察が動くケースは少ないでしょう。
警察に相談に行く前の証拠の保全方法

警察に相談に行っても、ネットで脅迫された証拠がなければ警察も動いてくれません。
ネットでの脅迫は、口頭での脅迫に比べて証拠が残りやすい特徴がありますが、投稿された掲示板やSNS、ブログによっては、投稿者が自分の投稿を削除したり編集できたりする機能が備わっている場合もあります。また、掲示板等のサイト運営者が投稿内容が不適切と判断して削除してしまうこともあります。
スマホやノートパソコンを警察署に持参して、いざ脅迫された投稿を警察官に見せようと思っても、削除や編集をされてしまっていれば手遅れです。そうならないためにも、ネットに脅迫的な投稿がされたのを確認したら、早急に証拠を保全しましょう。
具体的には、脅迫内容に該当するページをプリントアウトするか、スクリーンショットで画像として保存します。その際、必ずページのURLと投稿日時が記録されるようにしてください。それにより、もし問題のある投稿が削除された場合でも、特定のページ、特定の日時に当該投稿が存在したことを証明できます。
また、保存する際は、脅迫的な投稿の箇所だけでなく、その前後の文章も保存することが重要です。脅迫罪になる言葉とはにも書かれていますが、ある言葉が脅迫罪に当たるかどうかは、被害者と加害者のやり取りなどを全体的に見て判断されるものだからです。
ネットの脅迫で警察が動かない場合の対処法

弁護士に刑事告訴を依頼する
刑事告訴とは、警察や検察に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることです。
刑事告訴は犯人の刑事処罰まで求める手続きですので、被害届を提出する以上に加害者の逮捕が期待できます。
ただし、告訴を受理した警察には捜査義務等の複数の義務が科せられるため、警察は受理を渋ります。
正直、面倒くさいのが不受理の理由である場合が多いのですが、証拠不十分など別の理由をつけて受理を拒否してくることが多いでしょう。
この点、弁護士は犯罪事実を正確に申告し、受理してもらいやすい告訴状の書き方のポイントを知っています。
また、一般の方よりも弁護士名で告訴状を提出することで受理される率は上がりますので、加害者の処罰を強く望むのであれば、弁護士に刑事告訴を依頼した方が良いでしょう。
≫脅迫や恐喝されたらどう対処したらいいの?警察と弁護士はどう使い分ければいい?
加害者の身元を特定し慰謝料請求をする
警察が刑事事件として取り扱ってくれなかった場合でも、ネットで脅迫されたことによって被った精神的苦痛に対する慰謝料請求ができます。
弁護士に依頼すれば、加害者の身元の特定から慰謝料請求の交渉、支払わない場合の民事訴訟まですべて一任することができます。
また、弁護士による刑事告訴を交渉材料とすることで、加害者から支払ってもらう慰謝料の高額化も望めます。
当法律事務所では、ネットに脅迫的な投稿をしてしまった加害者からの相談も多く寄せられています。
「脅迫罪で逮捕される前に被害者に謝罪して早急に示談を締結したいです」と希望する加害者も少なくありません。
加害者と被害者、両者の立場や考えがわかるからこそ弊所では最善の解決方法を提案できます。
親身誠実に弁護士が対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|